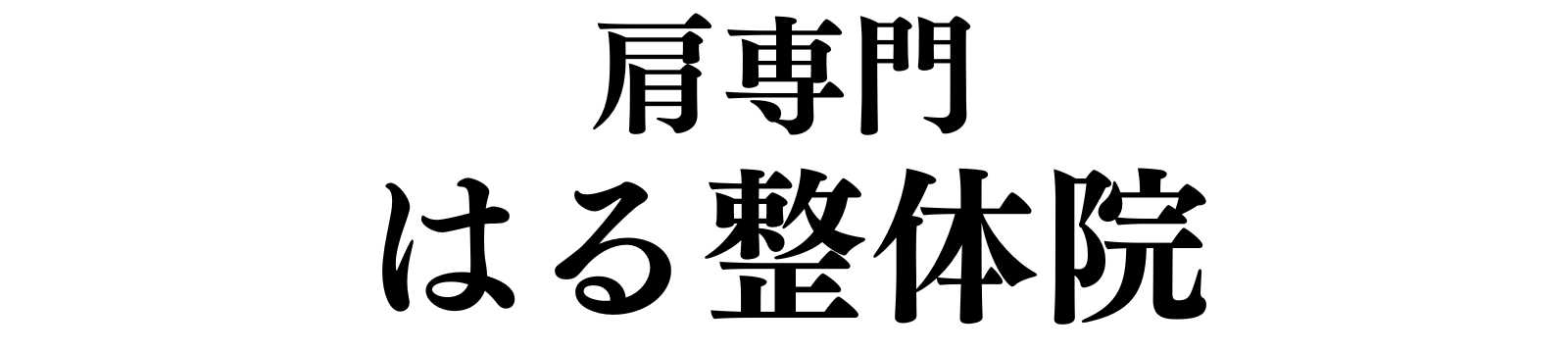五十肩のつらい痛み、温める?冷やす?その疑問に、明確な答えをお届けします。結論として、五十肩の適切な対処法は「急性期」と「慢性期」で大きく異なります。炎症が強い急性期には「冷やす」ことが基本であり、痛みが落ち着いた慢性期には血行促進のために「温める」ことが効果的です。この記事では、ご自身の五十肩がどの段階かを見極める判断基準から、時期に合わせた最適なケア方法、効果的なセルフケア、専門医の選び方までを網羅。症状改善と早期回復への具体的な道筋が明確になります。
1. 五十肩の症状は段階で変わる
「五十肩」とは、正式には肩関節周囲炎と呼ばれる疾患で、肩関節の周囲に炎症が起こり、痛みや動きの制限が生じる状態を指します。この五十肩の症状は、発症から回復に至るまで、いくつかの段階を経て変化していくのが特徴です。そのため、それぞれの時期に応じた適切なケアを行うことが、痛みの緩和と早期回復のために非常に重要となります。
一般的に、五十肩の進行は大きく分けて「急性期(炎症期)」「慢性期(拘縮期)」「回復期(解凍期)」の3つの段階に分けられます。この章では、特に「温める?冷やす?」の判断に大きく関わる急性期と慢性期の症状の違いに焦点を当て、その特性と対処法の方向性について詳しく解説します。
1.1 五十肩の急性期と慢性期の違い
五十肩の症状は、その時期によって痛みの性質や肩の動き、推奨される対処法が大きく異なります。ここでは、五十肩の進行における主要な二つの段階である「急性期」と「慢性期」それぞれの特徴を詳しく説明していきます。
【急性期(炎症期)】
急性期は、五十肩が発症して間もない時期で、肩関節周囲に強い炎症が起きている状態を指します。この時期は、何よりも痛みが強く、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
- 主な症状:
- 激しい痛み
特に肩を動かした時だけでなく、安静にしていてもズキズキとした痛みが続くことがあります。 - 夜間痛
寝ている時に肩の痛みが強くなり、目が覚めてしまう「夜間痛」が顕著に現れることが多いです。寝返りや特定の寝姿勢で痛みが悪化します。 - 熱感・腫れ
炎症が強いため、肩に熱っぽさを感じたり、わずかな腫れが見られることもあります。 - 可動域制限
痛みが強すぎて、肩を動かせる範囲が著しく制限されます。特に腕を上げたり、後ろに回したりする動作が困難になります。
- 激しい痛み
- 期間
一般的に、発症から数週間から数ヶ月程度続くとされています。 - 対処の方向性
炎症を抑え、痛みを緩和することが最優先となります。
【慢性期(拘縮期)】
慢性期は、急性期の強い炎症が徐々に治まり、痛みが軽減される一方で、肩関節の動きが悪くなる「拘縮(こうしゅく)」が進行する時期です。この時期の痛みは、急性期ほど激しいものではなく、安静時の痛みも軽減し、特定の動作時や動かし始めに感じる痛みが多いです。
- 主な症状:
- 可動域制限の進行
肩関節の動きが悪くなり、腕を上げたり、後ろに回したりする動作が困難になります。これは痛みが原因というより、関節を包んでいる組織や周囲の組織が硬くなるためです。 - 鈍い痛み
安静時の痛みは減少しますが、肩を動かしたり、無理な体勢をとったりすると、肩の奥の方に鈍い痛みを感じることがあります。 - 肩のこわばり
朝起きた時や長時間同じ姿勢でいた後に、肩が固まっているような感覚を覚えることがあります。
- 可動域制限の進行
- 期間
急性期の後、数ヶ月から1年以上続くこともあります。 - 対処の方向性
肩の可動域を改善し、柔軟性を取り戻すことが主な目的となります。
これらの違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 急性期(炎症期) | 慢性期(拘縮期) |
|---|---|---|
| 時期 | 発症直後〜数週間〜数ヶ月 | 急性期の後〜数ヶ月〜1年以上 |
| 主な症状 | 激しい痛み、夜間痛、熱感 | 可動域制限、鈍い痛み、こわばり |
| 痛みの性質 | 安静時もズキズキ、動かすと激痛 | 安静時は軽減、動かし始めや特定の動作で鈍痛 |
| 肩の動き | 痛みが強く、動かせる範囲が著しく制限される | 痛みは軽減するが、関節が固まり可動域が制限される |
| 推奨されるケア | 炎症を抑える | 血行促進、可動域改善、筋肉の緩和 |
1.2 時期に応じた適切な対処法の重要性
五十肩の症状が段階的に変化するからこそ、それぞれの時期に合わせた適切な対処法を選択することが極めて重要になります。誤ったケアは、症状を悪化させたり、回復を遅らせたりする原因となるため、注意が必要です。
例えば、急性期に炎症が強い状態で温めてしまうと、血行が促進され、かえって炎症を悪化させて痛みを増強させてしまう可能性があります。逆に、慢性期に入り、関節の拘縮が主な問題となっている時期に冷やし続けてしまうと、血行が悪くなり、筋肉の柔軟性が低下して回復が遅れることがあります。
2. 五十肩の「急性期」は熱感があれば「冷やす」が基本
特に発症初期の「急性期」には、激しい痛みや炎症がみられるのが特徴です。
痛みのある部位に熱感がある場合は「冷やす」ことが重要となります。
2.1 急性期の五十肩で冷却が大切な理由
五十肩の急性期は、肩関節の滑膜や関節包といった組織に炎症が生じ、それが痛みの主な原因となります。この時期に肩を冷やすことは、以下のような効果が期待できます。
- 炎症の抑制
冷却によって血管が収縮し、炎症部位への血流が一時的に減少します。これにより、炎症反応の拡大を防ぎ、腫れや熱感を抑える効果があります。 - 痛みの緩和
冷却は神経の伝達速度を遅らせる作用があるため、痛みの感覚を鈍らせ、一時的に痛みを和らげることができます。 - 組織損傷の拡大防止
炎症が強い状態が続くと、周囲の健康な組織にも影響が及ぶ可能性があります。冷却は、そうした二次的な組織損傷の拡大を防ぐ手助けとなります。
急性期に無理に温めたり、痛い箇所のマッサージをしたりすると、かえって炎症を悪化させ、痛みを増強させてしまう恐れがあります。そのため、急性期には「冷やす」ことが回復の第一歩となるのです。
2.2 効果的な冷却方法と注意点
急性期の五十肩に対する冷却は、正しく行うことで最大の効果を発揮します。以下に効果的な冷却方法と、実践する上での注意点を示します。
| 冷却材の種類 | 特徴と使用方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 氷嚢 (ひょうのう) | 氷と少量の水を入れた氷嚢は、患部に密着しやすく、冷却効果が高いです。 | 水が漏れないようしっかりと口を閉じる。 |
| 保冷剤 | 冷凍庫で冷やして使用します。手軽に入手でき、繰り返し使えるのがメリットです。 | 温度が0℃以下に下がる可能性があるため、必ずタオルや布で包んで使用する。 |
冷却の頻度と時間
冷却は、1回あたり10分程度を目安に行いましょう。あまり長く冷やしすぎると凍傷や皮膚障害のリスクがあります。1日に数回(2~3時間おきなど)、痛みが強いと感じる時に繰り返し行うのが効果的です。
2.3 炎症を抑えるための冷却ケア
冷却は急性期の炎症を抑えるための重要なケアですが、それだけでなく、炎症を悪化させないための総合的なケアが必要です。
- 安静の確保
痛みが強い急性期は、肩関節に負担をかけないよう、できる限り安静にすることが大切です。無理な動作や物を持つことは避けましょう。 - 鎮痛剤の使用
痛みがひどい場合は、市販の痛み止めや、病院から処方された鎮痛剤の使用も検討しましょう。これらは炎症と痛みを同時に抑える効果があります。
冷却とこれらのケアを組み合わせることで、急性期の炎症を効果的に抑え、慢性期への移行をスムーズにすることが期待できます。
自己判断が難しい場合や痛みが改善しない場合は当院までご相談ください。
熱感の有無にかかわらず、痛みが出はじめてから1週間以内の方は、早期に施術を行うことで改善が早まるケースが多いです。
3. 五十肩の「慢性期」は「温める」が効果的
五十肩の症状が落ち着き、激しい痛みが和らいできた時期は「慢性期」と呼ばれます。この時期には、肩関節周囲の血行を促進し、硬くなった筋肉や腱、関節を包んでいる袋を柔らかくすることが回復への近道になります。
3.1 慢性期の五十肩に温めるべき理由
慢性期における温熱ケアは、単に気持ちが良いだけでなく、科学的な根拠に基づいた回復促進効果が期待できます。主な理由は以下の通りです。
- 血行促進効果
温めることで血管が拡張し、患部への血流が増加します。これにより、酸素や栄養素が供給されやすくなり、組織の修復が促されます。また、疲労物質や老廃物の排出もスムーズになり、痛みの軽減に繋がります。 - 筋肉の柔軟性向上
温熱は、硬くなった筋肉や腱、関節包(関節を包んでいる袋)といった軟部組織の柔軟性を高めます。肩関節周囲の組織が柔らかくなることで、可動域が改善され、日常生活での動作が楽になります。 - 痛みの緩和効果
温かさは、神経の興奮を鎮める作用があり、痛みの感覚を和らげる効果があります。また、筋肉の緊張がほぐれることで、血行不良による痛みや凝りも軽減されます。 - リラックス効果
温かい感覚は心身をリラックスさせ、ストレスの軽減にも繋がります。ストレスは痛みを増幅させることがあるため、精神的なリラックスは回復過程において重要です。
3.2 血行促進と筋肉の緩和に繋がる温熱ケア
慢性期の五十肩には、様々な温熱ケアが有効です。ご自身のライフスタイルや症状に合わせて、適切な方法を選びましょう。
| 温熱ケアの種類 | 具体的な方法と効果 | ポイント |
|---|---|---|
| 入浴 | 全身を温め、血行促進と筋肉の緊張緩和を促します。湯船に浸かることで水圧によるマッサージ効果も期待できます。 | 38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分程度ゆっくり浸かるのが理想的です。入浴剤を活用するとリラックス効果も高まります。 |
| ホットパック | 電子レンジで温めるタイプや、お湯で温めるタイプなどがあります。患部を局所的に温め、深部まで熱を届けやすいのが特徴です。 | タオルで包むなどして、直接肌に触れないように使用し、低温やけどに注意しましょう。15~20分程度が目安です。 |
| 蒸しタオル | 水で濡らしたタオルを絞り、電子レンジで温めて使用します。手軽に用意でき、じんわりとした温かさが特徴です。 | 熱すぎないか確認し、火傷に注意して使用してください。冷めてきたら再度温め直しましょう。 |
| ホッカイロ | 衣類の上から貼るタイプが便利です。持続的に温めることができ、外出時にも活用できます。 | 肌に直接貼らず、必ず衣類の上から使用してください。同じ場所に長時間貼り続けると低温やけどのリスクが高まります。就寝時の使用は注意しましょう。 |
| 温湿布 | 温感成分(唐辛子のカプサイシンなど)が含まれており、貼ることでじんわりと温かさを感じます。薬効成分による鎮痛効果も期待できます。 | 説明書に従って使用し、皮膚に異常を感じたらすぐに剥がしましょう。 |
これらの温熱ケアは、ストレッチや運動を行う前に実施すると、筋肉や関節が柔らかくなり、より効果的に可動域を広げやすくなります。ぜひ積極的に取り入れてみてください。
3.3 効果的な温め方と注意点
温熱ケアを効果的に行うためには、いくつかのポイントと注意点があります。
- 適切な温度と時間
「心地よい」と感じる程度の温度が最も効果的です。熱すぎると皮膚に負担がかかり、低温やけどのリスクもあります。状態を見ながら調整しましょう。長時間やりすぎると、かえって疲労感が増すこともあります。 - 継続が重要
一度温めただけでは効果は一時的です。毎日継続して行うことで、徐々に血行が改善され、筋肉の柔軟性が高まります。 - 低温やけどに注意
特に使い捨てカイロやホットパックを使用する際は、肌に直接当てず、必ず衣類やタオルを挟んで使用してください。感覚が鈍っている場合や、就寝中の使用は特に注意が必要です。 - 痛みの変化を観察
温めている最中や温めた後に、痛みが強くなる場合は、すぐに温めるのを中止してください。まだ炎症が残っている可能性や、温熱が合わない体質である可能性も考えられます。無理は禁物です。 - 入浴時の注意
長湯しすぎると脱水症状を引き起こすことがあります。水分補給をしっかり行いましょう。また、湯船から立ち上がる際は、めまいや立ちくらみに注意してください。 - 温熱とストレッチの組み合わせ
温めて血行が良くなり、筋肉が柔らかくなった状態でストレッチを行うと、より効果的に可動域を広げることができます。温熱ケアの後に、無理のない範囲で肩のストレッチを取り入れることをおすすめします。
これらの注意点を守りながら、ご自身の体の状態に合わせて温熱ケアを実践し、五十肩の回復を促進しましょう。
4. 温める?冷やす?五十肩の判断基準
4.1 痛みの質と熱感で判断するフローチャート
五十肩の温冷判断は、症状の時期によって大きく異なります。ご自身の現在の状態を正確に把握するために、以下の判断基準を参考にしてください。特に痛みの種類と患部の熱感が重要な手がかりとなります。
| 症状のポイント | 時期 | 対処法 |
|---|---|---|
| 激しい痛み、夜間痛 熱感や腫れ 肩を動かすと激痛 ズキズキとした強い痛み 安静時も痛い 寝ると痛みが強くなる | 急性期 | 冷やす |
| 熱感や腫れはない 不意の動作で激痛 鈍い痛み重だるさ 肩のこわばりを感じる 特定の動きで痛い | 慢性期 | 温める |
これらの判断基準はあくまで目安です。症状は個人差が大きく、時期が混在することもあります。特に「動かした時の痛みは強いが、熱感はない」など、判断に迷う場合は次の項目を参考にしてください。
4.2 自己判断が難しい場合の対処法
ご自身の五十肩が急性期なのか慢性期なのか、あるいは両方の症状が混在しているのか判断に迷うこともあるでしょう。特に以下のような場合は、自己判断で対処を続けるのではなく、整形外科を受診する、もしくは当院までご相談ください。
- 上記のフローチャートで判断に迷う場合
- 痛みが非常に強く、日常生活に支障をきたしている場合
- 冷やしても温めても痛みが改善しない、または悪化する場合
- 症状が長期にわたり、一向に改善の兆しが見えない場合
- 肩以外の部位にも痛みやしびれがある場合
- 肩を動かしても痛みは強くならないが、常に痛みがある。
- 肩の可動域制限は殆どないが、一定の方向に肩を動かした時のみ痛みが強くなる
5. 五十肩の回復を早めるセルフケア
五十肩の症状は、適切なセルフケアを行うことで回復を早め、日常生活の質を高めることができます。ただし、セルフケアは無理のない範囲で行うことが重要です。
5.1 五十肩の可動域を広げるストレッチ
五十肩の回復期において、固まってしまった肩関節の可動域を少しずつ広げていくことは非常に重要です。以下のストレッチは、肩関節の柔軟性を高め、血行を促進するのに役立ちます。
コッドマン体操(振り子運動)
この体操は、肩関節への負担を最小限に抑えながら、関節の動きを促すことを目的としています。
- 準備
テーブルなどに健康な方の手を置き、体を少し前かがみにします。五十肩の腕は力を抜き、だらりと垂らします。 - 動作
垂らした腕を、体の揺れを利用して、前後に小さく振ります。次に、左右に、そして円を描くようにゆっくりと動かします。腕の重みを利用して自然に動かすことがポイントです。 - 回数
それぞれ10回程度、1日数回行います。 - 注意点
痛みを感じる場合は無理せず中止し、動きの範囲を小さくしてください。反動をつけず、ゆっくりと行いましょう。
壁伝い運動(ウォールクライミング)
壁を利用して、肩の屈曲(腕を前に上げる動作)や外転(腕を横に上げる動作)の可動域を段階的に広げます。
- 準備
壁の前に立ち、五十肩の腕側の手のひらを壁につけます。指先が壁を登っていくようにします。 - 動作
指を一本ずつ壁に沿って上へ滑らせ、痛みのない範囲で可能な限り腕を上げていきます。上がりきったら、ゆっくりと指を滑らせながら腕を下ろします。腕を横に上げる場合は、壁に横向きに立ち、同様に行います。 - 回数
5~10回程度、1日数回行います。 - 注意点
- 肩をすくめないように注意し、肩甲骨の動きも意識しましょう。痛みを感じる場合は無理せず、少し手前の位置で止めてください。
タオルを使った肩関節の回旋運動
肩関節の内旋・外旋の可動域を改善するためのストレッチです。
- 準備
両手でタオルの両端を持ちます。健康な方の手は上から、五十肩の腕は下からタオルを掴みます。 - 動作
健康な方の手でタオルを上に引き上げ、五十肩の腕が背中の下の方から上の方へ、痛みのない範囲でゆっくりと動くようにサポートします。次に、健康な方の手を下ろし、五十肩の腕が下がるようにします。 - 回数
5~10回程度、1日数回行います。 - 注意点
無理に引っ張らず、痛みを感じたらすぐに中止してください。呼吸を止めずに行いましょう。
5.2 日常生活での姿勢と動作の工夫
日常生活の中で肩への負担を減らし、五十肩の悪化を防ぎ、回復を促すための工夫は多岐にわたります。無意識に行っている動作を見直し、肩に優しい習慣を身につけましょう。
正しい姿勢の維持
日頃の姿勢は、肩関節への負担に大きく影響します。
- 座る姿勢
椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばし、肩の力を抜きます。パソコン作業などでは、画面の高さを調整し、肘が90度になるように心がけましょう。猫背にならないよう注意が必要です。 - 立つ姿勢
重心を意識し、左右の足に均等に体重をかけ、肩甲骨を軽く寄せるように意識します。長時間同じ姿勢を続けることは避け、適度に体を動かしましょう。
重いものを持つ際の注意
重いものを持つ動作は、肩に大きな負担をかけます。
- 持ち方
痛みがでている方で荷物を持たない。 - 運搬
可能であれば、台車やキャリーカートなどを利用し、肩への直接的な負担を減らしましょう。
寝る姿勢の工夫
睡眠中の姿勢も、五十肩の痛みに影響を与えることがあります。
- 仰向け
仰向けで寝る場合は、痛い方の腕の下に薄いクッションやタオルを挟むことで、肩関節の安定を図り、痛みを軽減できることがあります。 - 横向き
就寝中は難しいですが、意識して痛い方を下にして寝ることは避けましょう。健康な方を下にして寝る場合は、抱き枕などを利用して、痛い方の腕が前に出すぎないようにサポートすると良いです。
高い所の物を取る際の注意
腕を高く上げる動作は、五十肩にとって特に負担が大きい場合があります。
- 踏み台の活用
無理に腕を伸ばして届かない物を取ろうとせず、必ず踏み台や椅子を利用して、体の位置を高くしましょう。腕を高く上げすぎないように注意してください。 - 動作の工夫
可能であれば、健康な方の腕を使い、痛い方の腕は補助的に使うか、使わないようにします。
カバンを持つ際の注意
カバンの持ち方一つで、肩への負担は大きく変わります。
- 両肩掛け
リュックサックなど、両肩で重さを分散できるカバンを選ぶのが理想的です。 - 片方掛け
ショルダーバッグなどを片方の肩にかける場合は、痛い方の肩を避けて下さい。
6. 五十肩の専門的な治療と病院選び
五十肩の症状は、その時期や個人の状態によって様々ですが、自己判断だけで対処し続けると、症状が長引いたり、悪化したりする可能性があります。眠れないほどの痛みが続く場合は、整形外科医の診察を受けることをおすすめします。
6.1 整形外科での診断と治療法
整形外科では、五十肩(肩関節周囲炎)の診断と、個々の症状に合わせた治療が提供されます。五十肩だと思っていても、実際には腱板損傷や腱板断裂、石灰沈着性腱板炎など、別の疾患が隠れている可能性もあります。
正確な診断プロセス
五十肩の診断は、主に以下の手順で行われます。
- 問診
いつから、どのような痛みがあるか、日常生活での困りごとなどを詳しく聞き取ります。 - 視診・触診
肩の動きの範囲(可動域)や、特定の動作での痛みの有無、肩関節周囲の筋肉の状態などを確認します。 - 画像診断
- X線検査(レントゲン)
骨の異常や石灰沈着の有無を確認します。腱板損傷などの軟部組織の異常は直接写りませんが、五十肩と鑑別すべき他の疾患の可能性を探ります。 - MRI検査
腱板損傷や関節包の状態、炎症の程度など、軟部組織の詳細な情報を得ることができます。五十肩と似た症状を持つ他の疾患との鑑別において、非常に重要な検査です。 - 超音波検査(エコー)
リアルタイムで肩の動きを確認しながら、腱や滑液包の状態、炎症の有無などを評価できます。MRIよりも手軽に行える場合が多いです。
- X線検査(レントゲン)
これらの検査結果を総合的に判断し、五十肩であるかどうか、またその重症度や病期(急性期か慢性期か)を診断してくれます。
五十肩の主な治療法
五十肩の治療は、保存療法が基本となります。保存療法で改善が見られない場合や、症状が重度で日常生活に大きな支障をきたす場合には、手術療法が検討されることもあります。
| 治療法 | 具体的な内容 | 目的・効果 |
|---|---|---|
| 保存療法 | 薬物療法:内服薬(消炎鎮痛剤、筋弛緩剤)、外用薬(湿布、塗り薬)、注射(ステロイド、ヒアルロン酸、局所麻酔薬を用いた神経ブロック) | 痛みの緩和、炎症の抑制、関節の動きを滑らかにする |
| 理学療法: 運動療法:肩の可動域訓練、筋力強化訓練(理学療法士の指導のもと) 物理療法:温熱療法、電気療法、超音波療法など | 関節の拘縮改善、筋力回復、血行促進、痛みの軽減 | |
| 装具療法:サポーター、スリングなど | 肩関節の安静保持、保護、痛みの軽減 | |
| 手術療法 | 関節鏡視下手術:小さな切開でカメラを挿入し、関節内の炎症組織の除去、硬くなった関節を包んでいる袋を剥がすなどを行う | 重度の拘縮や強い痛みが保存療法で改善しない場合に、関節の可動域を回復させる |
これらの治療法は、患者さんの症状の段階(急性期か慢性期か)、痛みの程度、生活習慣などを考慮して、医師が最適なものを選択し、組み合わせながら進めていきます。
6.2 信頼できる医療機関を見つけるポイント
五十肩の治療を成功させるためには、信頼できる医療機関を選ぶことが非常に重要です。以下のポイントを参考に、ご自身に合った病院を見つけましょう。
- 整形外科専門医の有無
日本整形外科学会認定の専門医が在籍しているか確認しましょう。可能であれば、肩関節疾患を専門とする医師がいる病院を選ぶと、より専門的な知見に基づいた診断と治療が期待できます。 - 診断設備とリハビリテーション施設の充実度
MRIや超音波診断装置など、正確な診断に必要な設備が整っているか。また、理学療法士や作業療法士が常駐し、適切なリハビリテーションを受けられる施設があるかどうかも重要です。リハビリテーションは五十肩の治療において不可欠な要素です。 - 丁寧な説明とインフォームドコンセント
医師が患者の症状や状態、治療法について、分かりやすく丁寧に説明してくれるか。疑問や不安に対してもしっかりと耳を傾け、患者が納得した上で治療を進める「インフォームドコンセント」を重視しているかを確認しましょう。 - 治療方針の合致
保存療法を優先するのか、早期の回復を目指して積極的に治療を進めるのかなど、医療機関の治療方針がご自身の考えと合致しているかも大切です。 - 通いやすさ
治療やリハビリテーションは継続が重要です。自宅や職場からのアクセス、診療時間、予約の取りやすさなども考慮に入れると良いでしょう。 - セカンドオピニオンの推奨
診断や治療方針に不安がある場合、他の医師の意見も聞く「セカンドオピニオン」を推奨している医療機関は、患者中心の医療を提供していると言えます。
これらのポイントを踏まえ、いくつかの医療機関を比較検討することをおすすめします。インターネットでの情報収集はもちろん、実際に受診して医師やスタッフの対応を見ることも大切です。ご自身の体と向き合い、納得のいく治療を受けるために最適な医療機関を選びましょう。
7. まとめ
五十肩の痛みは、その時期によって適切な対処法が大きく異なります。急性期には炎症を抑えるために「冷やす」ことが基本となり、慢性期には血行促進と筋肉の緩和のために「温める」ことが効果的です。ご自身の痛みの質や熱感に注意を払い、適切な判断を行うことが早期回復への鍵となります。また、可動域を広げるストレッチや日常生活での工夫といったセルフケアも大切です。
再度になりますが、症状が改善しない場合や判断に迷う場合は、無理せず整形外科などの専門医を受診、もしくはお気軽に当院までご相談ください。